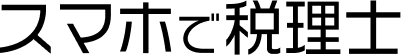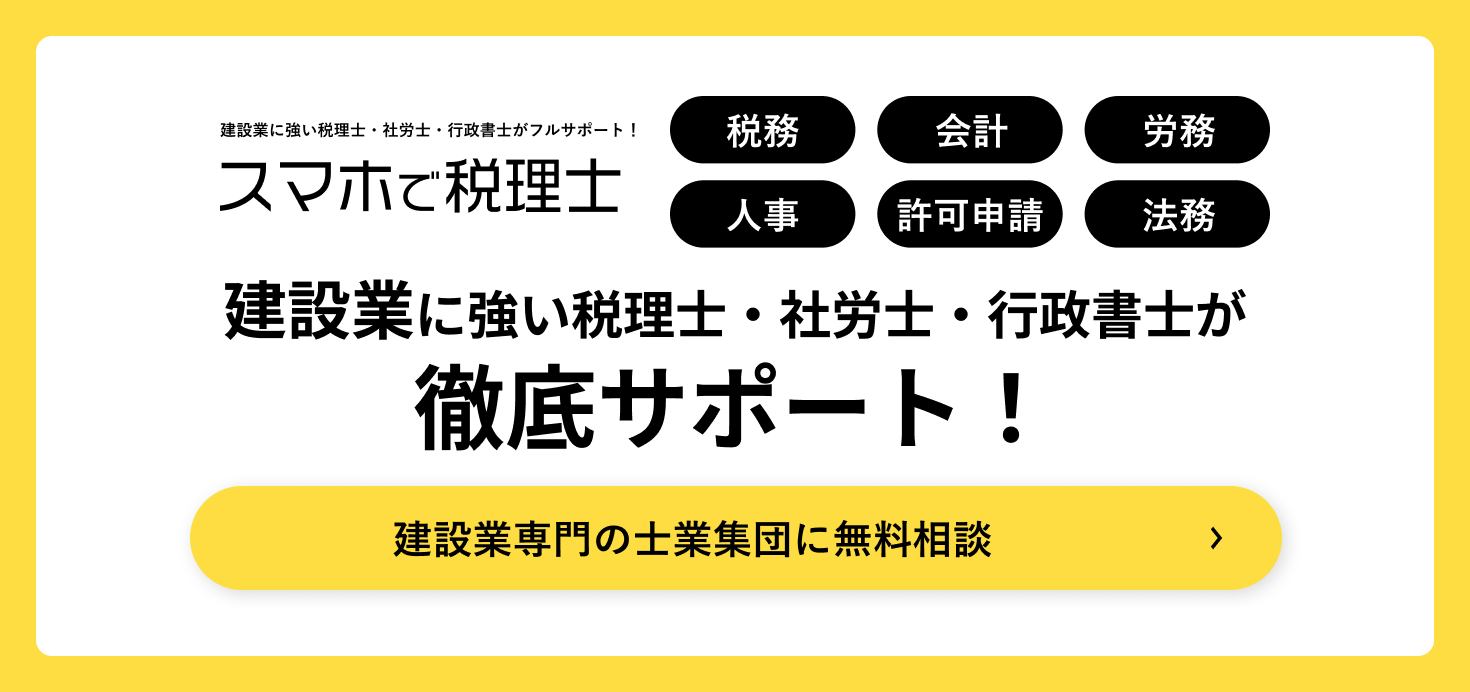建設業の簡易課税における事業区分(3種・4種・5種)完全ガイド
投稿日: 2025年11月28日 | カテゴリー: 建設業

建設業の簡易課税における3種・4種・5種の事業区分を徹底解説。資材調達や契約形態による違いを具体例で整理し、中規模建設会社の実務判断を支援します。
目次
なぜ「事業区分」が建設業者にとって重要か

建設業者が簡易課税制度を採用する最大の理由は、消費税計算における煩雑な仕入税額控除の事務負担を軽減できる点にあります。
しかし、誤った事業区分を適用すると、追徴課税や税務調査での指摘につながるリスクが高まり、経営に大きな影響を及ぼしかねません。
本記事では、建設業における第3種・第4種・第5種の事業区分の判定基準を網羅的に整理し、実務での正しい判断と対応策を明確に解説します。
建設業と簡易課税制度の基本理解

簡易課税制度とは
簡易課税制度とは、消費税の計算を簡略化するための仕組みで、基準期間(原則として2年前)の課税売上高が5,000万円以下である事業者が選択できます。建設業においても、規模によってはこの制度を利用するケースが少なくありません。
納税額は「売上にかかる消費税額 × 事業区分ごとのみなし仕入率」で算出します。これにより、実際の仕入や経費を細かく区分・計算する必要がなくなり、経理業務の効率化につながります。
ただし、簡易課税制度にはメリットとデメリットがあります。メリットは、帳簿作成や税額計算の負担が大幅に軽減される点です。一方で、経費比率が高い建設業者にとっては、みなし仕入率による計算が不利になる可能性もあり、慎重な判断が求められます。
事業区分(第1種~第6種)の体系
簡易課税制度では、事業内容に応じて6つの事業区分が定められており、それぞれに異なる「みなし仕入率」が適用されます。建設業者にとって特に重要なのは第3種・第4種・第5種ですが、全体像を理解しておくことが不可欠です。
- 第1種:卸売業(みなし仕入率 90%)
商品の仕入れと販売を行う卸売業。仕入割合が高いため最も高い仕入率が設定されています。 - 第2種:小売業(みなし仕入率 80%)
消費者へ直接販売する小売業。卸売に比べ経費比率が低く、仕入率もやや低めに設定されています。 - 第3種:建設業・製造業等(みなし仕入率 70%)
資材を購入し、自社施工や製造を行う業務。建設業の大半がこの区分に該当します。 - 第4種:加工賃・役務提供(みなし仕入率 60%)
資材を支給されて工事のみを行う場合や、役務提供中心の工事(足場組立など)が含まれます。 - 第5種:サービス業・運輸通信業等(みなし仕入率 50%)
建設業では設計や測量、コンサルティング業務など施工を伴わない役務が該当します。
建設業における事業区分の実務判断

建設業で簡易課税制度を適用する場合、第3種・第4種・第5種のいずれに該当するかの判定が重要です。誤った判断は税務リスクに直結するため、それぞれの定義や実務上の判断基準を正しく理解しておく必要があります。
第3種事業(建設業本来型)
第3種事業とは、主要な建設資材を自社で調達・購入し、施工を行ったうえで完成物を引き渡す形態を指します。これは建設業の典型的な形態であり、簡易課税制度では「みなし仕入率70%」が適用されます。
該当する例としては、建築工事、リフォーム、土木工事、電気工事、給排水設備工事などが挙げられます。これらは資材を自社で負担し、成果物を引き渡す「完成型工事」として分類されます。
判定のポイントは以下のとおりです。
- 資材調達を自社が負担しているか
- 施工業務そのものが主体であるか
- 成果物の引き渡しを伴うか
これらを満たす場合、基本的に第3種事業に区分されます。
第4種事業(役務提供型・加工賃型)
第4種事業は、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務提供に該当する業務であり、「みなし仕入率60%」が適用されます。
建設業でこの区分に該当する典型例は以下のとおりです。
- 足場の組立・解体、鳶工事、解体工事など役務中心の業務
- 元請から資材を無償提供され、施工のみを請け負うケース
- 修繕工事で資材が支給され、施工だけを行う場合
判定にあたっては次の点に留意する必要があります。
- 資材が無償提供か有償提供かで事業区分が変わる
- 契約形態や資材支給条件を必ず確認する
- 成果物の引き渡し型か、役務提供型かを重視する
つまり、資材調達の有無と業務内容の性質によって、第3種か第4種かの判定が分かれます。
第5種事業(サービス業・設計・技術系)
第5種事業は、サービス業・運輸通信業・技術サービス業などが含まれ、建設業の場合は施工を伴わない技術系業務が該当します。みなし仕入率は「50%」です。
建設業者が第5種に該当するケースには、次のようなものがあります。
- 建築設計業務(設計図面の作成など)
- 測量業務(土地調査、地盤調査など)
- 建築コンサルタント業務(施工管理指導、技術アドバイザリーなど)
判定の基準は、
- 工事そのものを伴わない役務提供主体の業務かどうか
- 日本標準産業分類で「技術サービス業」に属するかどうか
といった点です。施工と直接関わらない業務であれば、第5種事業として取り扱われます。
実践:複数事業を営む場合の取扱いと計算方法

原則法 vs 簡便法の理解
建設業者が複数の事業を営む場合、課税売上を事業区分ごとに分け、それぞれに対応するみなし仕入率を適用して計算する方法が「原則法」です。たとえば、第3種の建設工事と第4種の役務提供を同時に行う場合、両者を区分して計算する必要があります。
一方、売上を区分することが困難なケースでは、一定の条件を満たす場合に限り「簡便法」を用いることができます。簡便法では、合算した売上全体に一つの加重平均的なみなし仕入率を適用しますが、利用できる範囲には制約があるため注意が必要です。
計算例:第3種+第4種併用ケース
具体例として、売上の内訳が建設工事8,000万円(第3種)、足場工事2,000万円(第4種)の場合を考えます。
- 原則法の場合
・建設工事8,000万円 × 70%(第3種みなし仕入率)
・足場工事2,000万円 × 60%(第4種みなし仕入率)
→ 各区分ごとに仕入控除額を算定し、納付消費税額を合計します。 - 簡便法の場合
・総売上1億円に対し、加重平均で算出されたみなし仕入率を適用します。
・この方法により計算は単純化されますが、原則法より納税額が増減する場合があるため、事前のシミュレーションが不可欠です。
注意すべき実務上の論点・リスク・FAQ

更新・法令改正のチェック
建設業における簡易課税制度の適用は、消費税法令の改正や国税庁通達の更新によって影響を受ける可能性があります。特に、2023年10月から導入されたインボイス制度(適格請求書保存方式)では、取引先からの仕入税額控除の要件が厳格化され、制度利用時の帳簿・請求書管理がこれまで以上に重要となりました。定期的に国税庁の最新情報を確認し、自社の経理体制に反映することが求められます。
よくある誤り・リスク
建設業者が簡易課税制度を利用する際、次のような誤りがしばしば見受けられます。
- 第3種と第4種の区別が曖昧なまま、誤ったみなし仕入率を適用してしまうケース。
- 複数事業の売上管理が不十分で、正確な按分計算ができないことによる税額の過少申告リスク。
- 簡易課税の2年間縛り:一度選択すると、原則として2年間は制度変更ができないため、事前のシミュレーションが不可欠です。
- 固定資産譲渡の扱い:自己使用していた機械や設備などを売却した場合は「第4種事業」に分類されるため、通常の工事売上と混同しないよう注意が必要です。
これらを軽視すると、税務調査での指摘や追徴課税につながる可能性があります。
ケーススタディ(中規模建設会社向け実例)
具体的な事例を通して、誤りやリスクを確認しておきましょう。
- 例1:建築+設計事業を営む企業
施工業務は第3種に該当する一方、設計業務は第5種に分類されました。売上区分を明確にせず一律に第3種として計算した場合、税額が過少計上となり税務リスクが高まる可能性があります。 - 例2:資材提供を受けて足場業務を請け負う企業
自社で資材を調達しないため、第4種事業に該当しました。もし第3種として処理していた場合、みなし仕入率の差(70%と60%)により税額が変動し、後に修正申告が必要となるリスクがあります。
これらのケースからもわかるように、契約形態や資材調達方法を精査し、正しく区分判定することが不可欠です。
まとめと実践アクション

建設業者が簡易課税制度を正しく活用するためには、まず自社の事業形態を棚卸し、資材調達方法や契約形態を整理することが出発点となります。判定に迷う場合は、税理士などの専門家に相談し、ダブルチェックする体制を持つことが望ましいでしょう。
また、複数事業を営む企業では、売上の正確な按分ルールや簡便法の可否を事前に確認しておく必要があります。さらに、税制改正や国税庁の通達を定期的にチェックする仕組みを社内に設けることで、制度変更に迅速に対応できます。
本記事で示した内容を実務に落とし込むことで、税務リスクを回避しながら効率的な経営管理を実現できるはずです。ぜひ一度、自社の区分判定や制度利用状況を見直し、必要に応じて専門家へご相談ください。